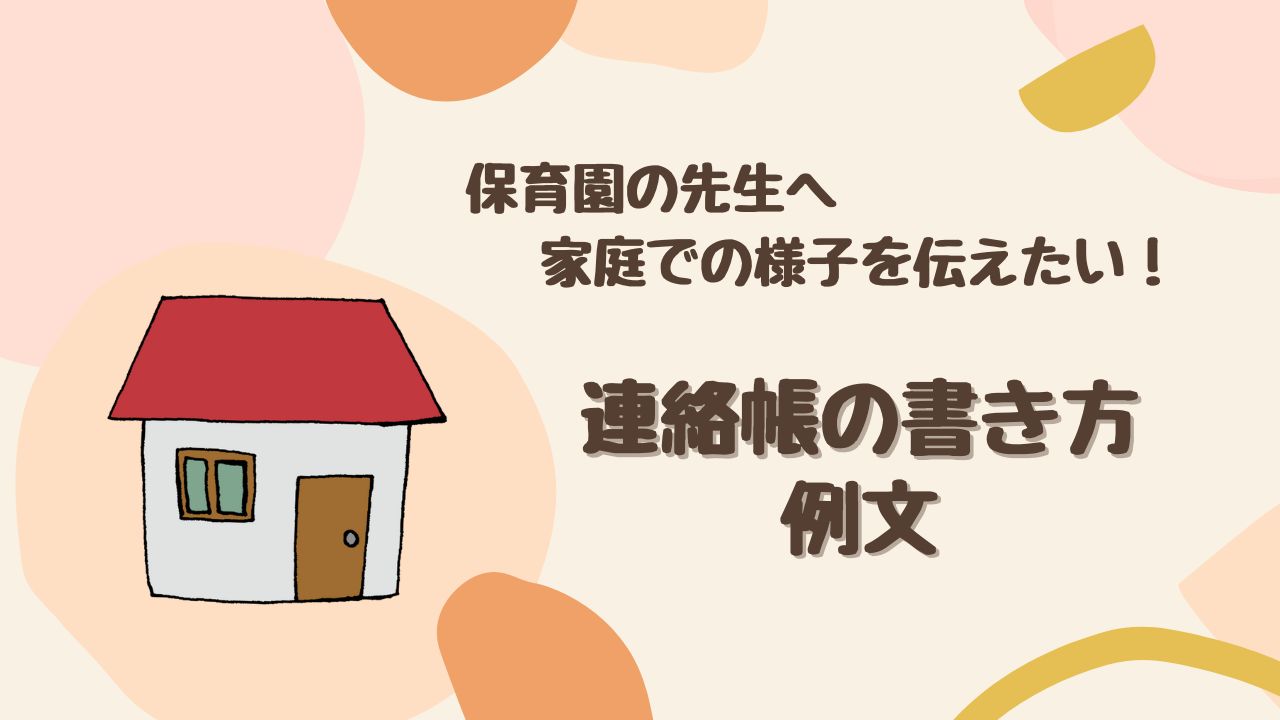保育園の連絡帳の「家庭での様子」欄に何を書いたら良いか困るという方は多いでしょう。
書きたいことがあっても良い文章が思いつかないと悩んでいる方もいるかもしれません。
この記事では、家庭での様子を書く例文を16個紹介します。
また、「家庭での様子は書き尽くして、もう書くことない」となった時に使えるネタも7個紹介していますよ。
もう連絡帳の書き方に困ることはなくなります!
連絡帳に書くことがない…と頭を抱える毎日とオサラバしたい人は、ぜひ最後までご覧ください。
0歳児、1歳児、2歳児の保護者で、年齢に応じた連絡帳の例文が知りたいという方はコチラの記事も参考にしてくださいね。
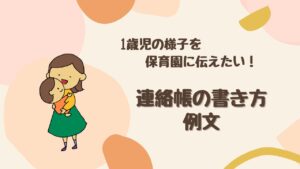
保育園の連絡帳に書いてはいけないことは? 気をつけることを紹介
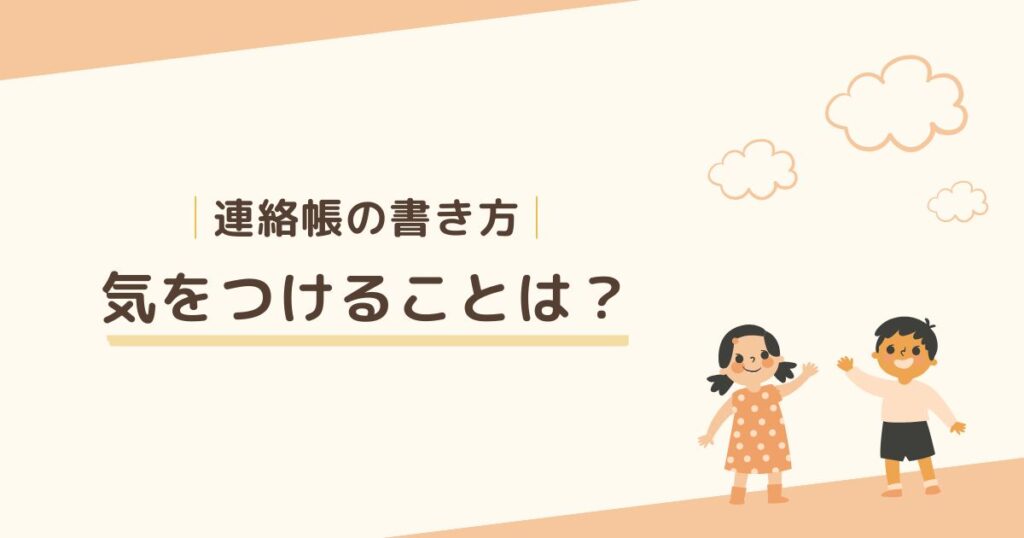
連絡帳に書くことがなくて悩んでいると、思いついたネタは何でも使いたくなりますよね。
しかし、ネタ選びや書き方を間違えると、先生に迷惑をかける可能性があります。
連絡帳を書く前に、書いてはいけないこと、気をつけることをチェックしておくと安心できるでしょう。
それぞれの注意点について、詳しく解説します。
1.要望やクレームは書かない
保育園の連絡帳には要望やクレームの記載は控えましょう。
連絡帳は主に文字だけでのやり取りになるため、伝えたい意図が正確に伝わらず、誤解を招く可能性があります。
特に感情的な表現や曖昧な言い回しは、相手の受け取り方によって意図と異なる解釈をされる可能性があるため、注意が必要です。
どうしても要望やクレームを伝える必要がある場合は、「後日お電話します」と伝えるのが良いでしょう。
保育士との直接的なコミュニケーションの場を設けることで、内容をより正確に伝えることができます。
先生との良好な関係を保つためにも、ネガティブな内容は慎重に取り扱い、適切な方法で伝えることを心がけましょう。
2.長文は書かない
保育園の連絡帳は、できるだけ簡潔な文章で書くことが大切です。
保育士は多くの子どもたちを見守りながら、限られた時間の中で多くの情報に目を通しています。
長文だと負担が増え、伝えたい重要なポイントが埋もれてしまう可能性があります。
内容は1〜2文にまとめるよう心がけましょう。
もし文章が長くなる場合は、箇条書きを使うことで読みやすくすることができます。
保育園との円滑な連携を実現するには、簡潔で要点が伝わりやすい文章が必要です。
相手の時間を考慮しながら、必要な情報を的確に伝える工夫をしましょう。
<例文>保育園の連絡帳「家庭での様子」の書き方16種類を紹介
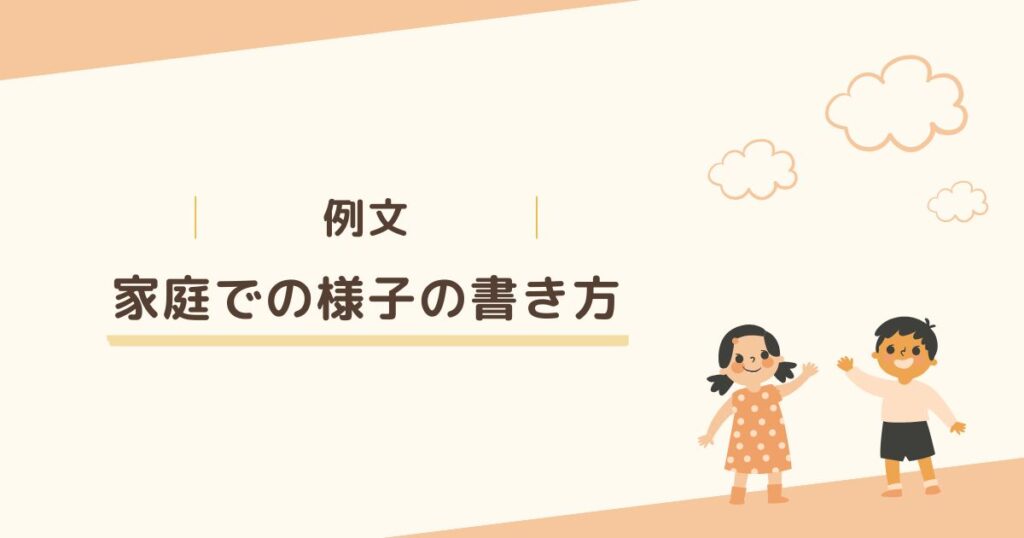
保育園の連絡帳へ家庭での様子を書く時に使えるネタを16個紹介します。
それぞれのネタについて連絡帳の書き方を解説しているため、参考にしてくださいね。
例文はテンプレートとしてそのまま使えるため、ぜひ活用してください。
1.体調の変化・ケガ
鼻水や咳が出る、いつもより柔らかい便が出たなど、体調の変化は忘れずに伝えたいですね。
他にも、あせもなどの皮膚トラブルや「昨夜、頭を打った」といった怪我も連絡帳に書いておくと、保育中に気になることはないか、注意して見守ってもらえるでしょう。
体調の変化やケガを伝える時に使える例文は、次のとおりです。
本日、朝から鼻水がいつもより多く出ています。
状態が続くようであれば、病院を受診しようと考えています。
園での様子や気になる体調の変化があれば教えていただけると助かります。
2.食事の内容
何をどの程度食べたかも、子どもの体調を見守る上では重要な情報です。
いつもより食べる量が少なければ、風邪のひきはじめかもしれないと注意して見守ることができます。
ヨーグルトやチーズを大量に食べた場合、保育中に軟便になる可能性があるため、伝えておくと良いでしょう。
今朝は朝食でブルーベリーヨーグルトをたくさん食べました。
とても気に入った様子で、おかわりを何度もしたので、お腹を壊さないか心配しています。
今のところ体調に問題はありませんが、園での様子に変化があれば教えていただけると幸いです。
3.睡眠時間
睡眠時間が短い時は早くお昼寝を促すなど、保育士が家庭での様子に合わせた対応を取れるので、連絡帳で伝えておくと良いでしょう。
寝る前のエピソードも一緒に伝えると、ネタとして何度も使いまわすことができますよ。
昨夜の睡眠時間はいつもより短めでした。
寝る前に「コチョコチョ遊び」を始めたら楽しくなってしまい、なかなか寝付けませんでした。
そのため、保育中に眠くなってしまう可能性があります。
午前中の様子を見ていただけると有難いです。
4.予防接種をしたこと
予防接種の翌日は、副反応で微熱が出たり、接種部分を痛がったりするかもしれません。
予防接種をしたことを伝えておくと、何かの反応が出た際に先生が対応しやすくなるので安心ですよ。
昨日、左腕の二の腕に予防接種を受けました。
今のところ普段と変わらず元気ですが、接種部位をかゆがったり痛がったりしないか、心配しています。
園での様子についても気になる点があれば教えていただけると助かります。
5.前日の様子
家で見せる姿は、保育園で体験したことに影響されていることが多いです。
我が子もある日を境に「どーこだ」「ここでしたー」と口ぐせのように言うようになりました。
連絡帳に書いてみると、金魚を探す絵本を気に入って何度も見ていたとのこと。
いつもと違った前日の様子を話題にすると、園での姿をより詳しく聞く機会になるかもしれません。
昨日、保育園から帰宅した後、カーテンに隠れたり出てきたりしながら「どーこだ」「ここでしたー」と繰り返して遊んでいました。
これまであまり見たことのない遊び方で、新しいことを始めた様子がとても微笑ましかったです。
私まで楽しくなり、一緒にカーテンで遊びました。
6.週末の過ごし方・おでかけ
週末の過ごし方を連絡帳に書くと、保育士が子どもに話しかける時、話題にすることができます。
子どもも楽しかった話を聞いてもらえるので、きっと喜びますね。
週末に家族でショッピングモールへ行きました。
おもちゃ売り場でうさぎのぬいぐるみをとても気に入り、手放さなかったので購入しました。
それ以来大切にしており、昨夜も抱っこして寝ています。
園でもこのぬいぐるみの話をするかもしれません。
7.最近できるようになったこと
子どもが最近できるようになったことを伝えておくと、保育士が気付いた時に褒めることができます。
家族だけでなく、保育園でも褒められると嬉しい上に自信もつくので、子どもにも良い体験になりますね。
最近、ごはんの後に自分で食器を洗い場まで運ぶようになりました。
とても褒められるので得意げにしており、家族にも「食べ終わったら持って行くんだよ」と教えています。
その姿はまるで小さなお母さんのようで、見ていてとても微笑ましく感じています。
8.好きな遊び・ハマっていること
保育園は集団生活の場ですが、すんなりみんなの輪の中に入っていける子ばかりではありません。
保育士が好きな遊びやハマっていることを知っていると、「〇〇を一緒にやろう」と誘うことができるので、伝えておくことがオススメです。
最近、おままごとに夢中になっています。
赤ちゃん役にしたぬいぐるみを何体も並べて、「ごはんだよ」と言いながら作った料理を一生懸命食べさせています。
お世話をする姿がとても可愛らしく、成長を感じています。
9.好きなテレビ番組・キャラクター
好きなテレビ番組やキャラクターを伝えておくと、子どもの気分を盛り上げる手助けとなります。
「保育中いつもニコニコ」というわけにはいかず、気に入らないことが起きて泣いてしまうこともあるでしょう。
先生が好きなキャラクターを知っていると「あっちに〇〇のおもちゃがあるよ」など、気分を変える声かけがしやすくなりますよ。
最近は〇〇(キャラクター名)が大好きで、テレビを見た後に決めセリフを楽しそうにマネしています。
家族にも披露してくれて、みんなで笑顔になる瞬間が増えました。
園でも〇〇の話をするかもしれませんので、お付き合いいただきますと幸いです。
10.忘れたくないセリフ
連絡帳は先生との連絡手段ですが、大きくなっても残る育児日記のようなものでもあります。
子どもが日々話す印象的な言葉や、忘れたくないセリフをメモのように残しておくのも良いですよ。
今朝、私が忘れ物をして慌てているときに、子どもが「ママ、ぼくがいるから大丈夫だよ」と言ってくれました。
その一言がとても心に響き、思わず抱きしめたくなりました。
小さな励ましに助けられる場面が増え、成長を感じる瞬間でした。
11.可愛かった出来事
連絡帳を育児日記のように使って、忘れたくない可愛かった出来事を書くのも良いでしょう。
子どもが大きくなって見返す時に、ホッコリした気分になれますよ。
〇〇(子どもの名前)の誕生日会で「大きくなったら何になりたい?」と聞いたところ、「うさぎになりたい!」と言って、ピョンピョンと跳ねて見せてくれました。
その姿がとても可愛らしく、思わず笑顔になりました。
楽しい時間を一緒に過ごせて幸せを感じました。
12.子どもがこだわっていること
「靴を自分で履きたがる」など、子どもがこだわっていることを先生に伝えておくと、保育園でも手伝わず見守る等の対応をしてもらえるかもしれません。
特に、子どもがこだわっていることに手を出されると怒って泣き叫んでしまう場合は、あらかじめ伝えておくことがオススメです。
かんしゃくを起こす機会を減らせることで、子どもと先生の負担も減らすことができますよ。
最近、自分で靴を履くことに強いこだわりを見せています。
急いでいる時に手伝おうとすると「自分でやる!」と泣いて怒ることがあり、成長の証だと感じています。
多少時間がかかりますが、満足げな顔を見ると応援したくなります。
13.トイレトレーニングの様子
子どもはどうしても保育園で過ごす時間が長くなるため、トイレトレーニングを進める上で連絡を取り合うことは必須になります。
家庭での様子が分かっていると、先生も「保育園でトイレに誘う時はこうしよう」などの工夫をしやすくなりますよ。
最近、トイレに行きたいと教えてくれるようになり、一緒に選んだ大好きなウサギ柄のパンツをとても嬉しそうに履いています。
まだトイレでの排泄は成功していませんが、やる気に満ちた表情を見せてくれており、成長を感じています。
園でも引き続き見守っていただけると嬉しいです。
14.叱ったこと・困っていること
家で困っている行動を保育園でもしていないか、気になりませんか?
家庭内で困っていること、叱ったことを話題にして、園の様子を聞いてみると良いでしょう。
何か対応のヒントが見つかるかもしれません。
昨日、妹を叩いて泣かせてしまったため、手を出すのはよくないと伝えました。
家では興奮するとすぐに手が出てしまうことがあり、保育園でもお友達に同じようなことがないか心配しています。
もし園で気になる様子があれば教えていただけると助かります。
15.保育園での出来事を家で話したこと
子どもの話をネタにして、保育園でどんな活動をしているのか聞いてみると良いでしょう。
園でハサミを使い始めたから家でも使ってみるなど、同じ遊びを家でも取り入れると、休日の過ごし方の幅が広がりますよ。
保育園でハサミを使ったことを嬉しそうに教えてくれました。
「チョキチョキ」と言いながら手で使うマネをして楽しそうに見せてくれています。
これまで怖くて使わせていませんでしたが、家でも挑戦させようと思います。
16.楽しんで登園している様子
子どもから「〇〇先生が好き」「早く保育園行きたい」など、登園を楽しみにしている発言が聞かれたら、ぜひ先生に報告しましょう。
保育園が楽しいと思ってくれることは、先生にとって嬉しいことなので、きっと喜んでもらえますよ。
保育園がとても楽しいようで、朝から「早く保育園に行きたい!」と張り切っています。
また、お迎えの際には「もう少し遅く来て」と言うほど名残惜しいようです。
園での毎日が充実していることが伝わり、安心しています。
家庭での様子は書くことない…使えるネタを7つ公開
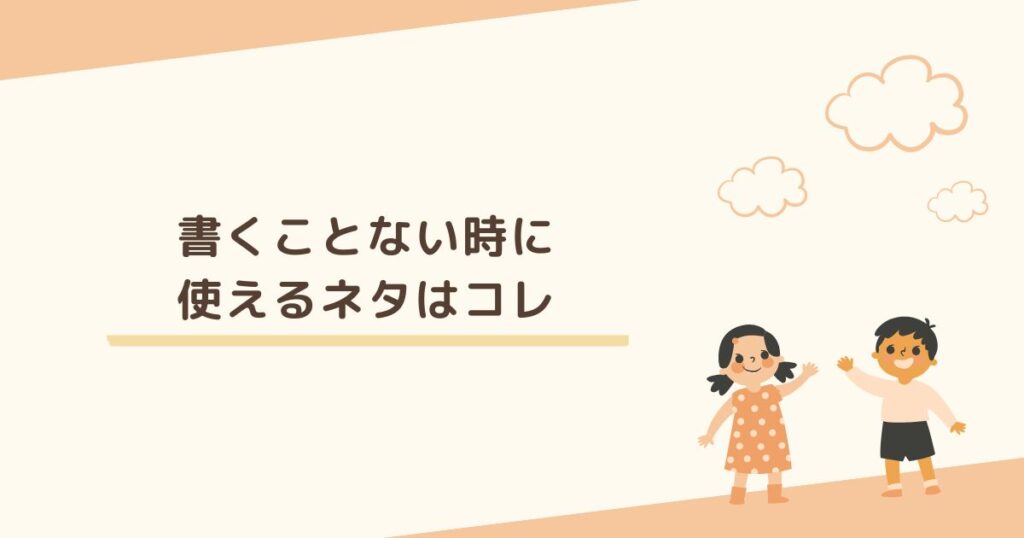
家庭での様子を書き尽くして「もう書くことない…」悩んでいる方も多いでしょう。
そんな時に使えるネタを7つ紹介しますね。
それぞれの例文や書き方を紹介します。
テンプレートとしてもそのまま使えるため、困ったらマネしてくださいね。
1.お迎えなどの連絡事項
お迎えに行く人や時間など、いつもと違うパターンの時には、連絡帳を使ってお知らせすると良いでしょう。
定期的に通っている病院がある場合も、連絡帳を通じて受診予定を共有しても良いですね。
今朝から鼻水が出ており、病院を受診するため、本日のお迎え時間は通常より早くなります。
母方祖母が15時頃に迎えに行きますので、どうぞよろしくお願いいたします。
2.行事の感想やお礼
運動会やお遊戯会などの行事の後は、感想やお礼を書くのも良いでしょう。
子どもたちの成長が見えて感動した、先生が時間をかけて準備したことがよく分かる素敵な行事だったなど、話題にできることは多くありますよ。
先日の運動会では、大きな声で返事をしたり、一生懸命走る姿に成長を感じ、感動しました。
子どもの頑張りだけでなく、先生方の丁寧な準備や進行のおかげで素晴らしい行事となり、心から感謝しています。
思い出深い一日をありがとうございました。
3.保育園での様子を聞く
お迎えの時、保育中の様子を詳しく聞きたいと思っても、先生が忙しそうで遠慮してしまうという方もいるかもしれません。
そんな時は、連絡帳を使って園内での様子を聞いてみると良いですよ。
保育園ではどのような遊びや活動に興味を持っていますか?
家ではテレビを見る時間が多く、他の遊びにあまり興味を示しません。
保育園で楽しんでいることを家でも取り入れてみたいと考えているため、教えていただけると助かります。
4.前日の先生コメントへ返信をする
先生が書いてくれるコメントの中には、読んでいて笑ってしまうもの、感心するものもあります。
コメントを読んで感じたことをお返事として書いてみましょう。
我が子の連絡帳には、『おままごと中に「何が入ったケーキなの?」と聞いたら「イチゴとみかんと…切り干し大根」と教えてくれました』と書かれていて、大笑いしたことがあります。
このコメントに返事をするとしたら、次のような書き方ができますよ。
保育園で食べた切り干し大根が美味しかったようで、大好物になりました。
好きな食べ物だとは知っていましたが、ケーキの具材にまで使うとは驚きです。
発想の豊かさに思わず笑ってしまいました。
今後も楽しい様子を聞けるのを楽しみにしています。
5.休み明けや新年など保育初日の挨拶
長期間お休みした後や新年など、保育が始まる日には挨拶文を書くと良いでしょう。
あけましておめでとうございます。
昨年は、日々の成長を丁寧に見守っていただき、本当にありがとうございました。
特に運動会で全力で走る姿に成長を感じ、感動したのを覚えています。
今年も子どもとともに楽しい一年を過ごせればと思っています。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
6.年末や保育最後の日の挨拶
年内最後の保育の日は、年末の挨拶を書くと良いでしょう。
今年一年、大変お世話になりました。
おかげさまで運動会や発表会など、多くの行事を通して子どもの成長を実感することができました。
特に、練習した歌を家で披露してくれたときは感動しました。
先生方のご尽力に心より感謝しています。
来年もよろしくお願いいたします。
進級や卒園、先生の退職等で、お別れする時の挨拶を連絡帳に書きたいと考える方も多いかもしれません。
保育園が最後の日に先生へお礼を伝える連絡帳の書き方は、コチラの記事で紹介しているため、参考にしてくださいね。
7.トラブルの相談をする
保育園から帰ってきたら、子どもが「〇〇君にいじめられる」と言って泣いている…
親としてはとても心配になりますよね。
トラブルの相談は、文章として残ってしまう連絡帳では避けた方が良いでしょう。
連絡帳では、「相談する時間を作って欲しい」「電話で話したい」とお願いし、先生に直接話す方法がオススメですよ。
子どもがお友達との関係で少し困っている様子があり、詳しく相談させていただきたいと思っています。
お手数ですが、電話でお話しできる時間をいただけると助かります。
先生のご都合の良い日時があれば教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
お友達とのトラブルがあった時の連絡帳の書き方は、コチラの記事で詳しく紹介しています。
小学生向けの内容ではありますが、参考になる部分も多いので、気になる方はぜひご覧ください。
保育園の連絡帳は毎日必要? ネタ切れして書くことない時の対処法
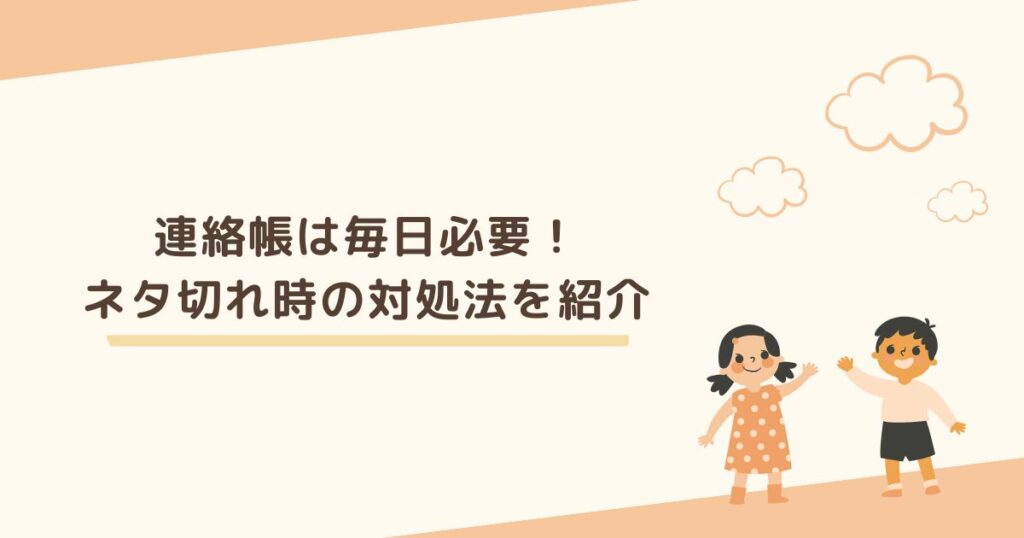
保育園の連絡帳は、毎日書いた方が良いでしょう。
この章では、連絡帳への記入が毎日必要な理由と、どうしても書くことがない時の切り抜け方を紹介します。
保育園の連絡帳を毎日書いた方が良い理由
保育園の連絡帳を毎日書いた方が良い理由は、子どもが快適に過ごすためです。
連絡帳を通じて子どもの普段と違う様子を保育士に伝えれあれば、保育中の様子を注意して見守ることができます。
例えば、前夜よく眠れていなければ、早めにお昼寝に誘うなどの配慮が行われます。
お腹の調子を崩していれば、辛そうな様子はないかを注意深く観察してもらうことができるでしょう。
連絡帳で家庭での様子を伝えることで、保育士は子どもの様子の特に注意すべきポイントが分かり、いち早く不調に気付けるようになります。
親と保育士の連携が深まることで、子どもが安心して楽しく過ごせる保育環境が整うでしょう。
どうしても書くことない時の切り抜け方
どうしても書くことがない時は、「いつもと変わりありません」「今日も元気です」の1文でも良いので書くようにしましょう。
保育士にとって、この一文は家庭で特に気になることがないと確認できる大切な情報です。
逆に何も書かれていない場合は、保育士側も状況を把握することが難しくなる可能性があります。
普段と違う様子の有無だけでも伝える習慣をつけることで、子どもの変化が見逃されるリスクを軽減できます。
忙しい朝でも数秒で簡単に書ける内容なので、できるだけ毎日記入を心がけると良いでしょう。
保育園の連絡帳はいつ書くと良いかを徹底解説

保育園の連絡帳は、当日の朝に書くのが理想的です。
朝の様子や気になる点など、最新の情報を記載できるため、保育士にとっても子どもの状態を正確に把握する助けになります。
ただし、朝は忙しく時間が取れないことも多いかもしれません。
その場合は、前日の夜にあらかじめ書いておく方法もあります。
朝になってから何か気になることがあれば、短い一文でも追記するとより有効です。
「今日は少し食欲がありません」「今朝は元気に遊んでいました」など簡潔に記載するだけで、保育士との情報共有がスムーズになります。
最新の状況を伝えることで、子どもの快適な保育環境づくりにつながります。
<まとめ>保育園 連絡帳の家庭での様子は、育児日記の感覚で書くとラク

この記事では、家庭での様子を書く例文とそれ以外のネタ23種類を紹介しました。
「保育園の先生が読む文章だ…」と考えると身構えてしまう人も多いでしょう。
子どものありのままの姿を育児日記の感覚で書くと負担が減る上、保育士にも子どもの様子がキチンと伝わります。
子どもが大きくなってから読んだらホッコリするだろうなぁと思うような出来事をメモのように書き残しておけると良いですね。
何を書くかどうしても迷ってしまう方は、この記事のネタや例文を参考にしてくださいね。